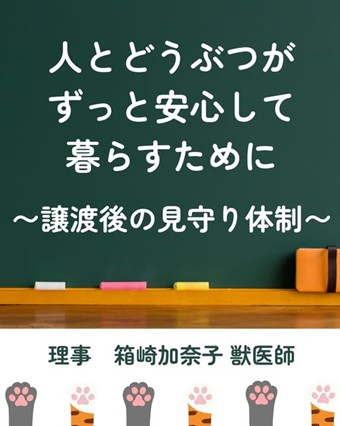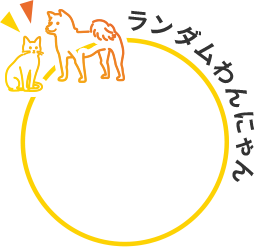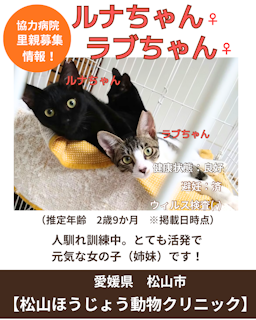========
人とどうぶつがずっと安心して暮らすために:譲渡後の見守り体制
獣医師:箱崎 加奈子
========
はじめに
譲渡活動において、譲渡時に他者の支援が必要な状況のご家庭には譲渡をしないという判断は、保護どうぶつの福祉と安全を守る上で一般的な判断かと思います。
譲渡の時点では、飼育の継続が現実的であり、責任をもって迎え入れる意思と環境が整っていることが求められます。
しかし、人の暮らしは常に変化しています。
譲渡時には問題がなくとも、年月の経過とともに、健康状態の悪化や家族構成の変化など、環境が大きく変わることは予想の範囲内です。
だからこそ、譲渡は「終わり」ではなく、「始まり」と捉え、継続的な見守り体制が必要であると感じています。
見守りが必要になる背景
実際に、譲渡後に起こりうる変化は少なくありません。
たとえば…
◉ 飼い主が高齢となり、通院や介護が必要になる
◉ 飼い主の病気やけがによって、動物の世話が困難になる
◉ 経済的な理由やその他事情により、飼育が継続できなくなる
◉ 飼い主が亡くなってしまい、動物がひとり取り残される
こうした状況は、どんなご家庭にも起こりうる可能性があり、譲渡時の条件だけでは予測しきれません。
だからこそ、譲渡後も寄り添い続けられる「見守り」の仕組みが重要になります。
継続的な見守りとは何か
見守りとは、監視や管理ではありません。大切なのは、「困ったときに声をあげやすい関係性をつくること」。
具体的には…
◉ 定期的な近況確認(通院時の様子、LINEや電話でのやりとり)
◉ 飼い主の様子に何か気になる変化を感じたときの早期フォロー
◉ トライアル期間だけでなく、譲渡後数ヶ月~数年先を見越した関わり
また、譲渡家庭の状況によっては、一時預かりや再譲渡の選択肢を提案するケースも出てくるかもしれません。
柔軟な対応ができるように、あらかじめ選択肢を示しておくことも見守りの一部です。
地域連携とその課題
一時預かりや再譲渡など、万が一の対応が必要となった場合に備えるためには、動物病院単独での対応では限界があります。
保護団体、ボランティア、行政との連携が不可欠でしょう。
しかし、現状ではこうした連携が十分に機能しているとは言えず、支援が必要な状況が発生しても、スムーズな対応が取れないことが少なくありません。
たとえば、譲渡家庭からのSOSが病院に届いても、その後に受け皿が見つからず、困り果ててしまうケースも見られます。
これからの課題は、「情報の共有」と「役割分担」、そして「日頃からのネットワーク構築」です。
「もしものとき」に助けを求められる関係性を築くことが、動物と人の安心につながります。
動物病院の役割
動物病院は、保護どうぶつの譲渡に関わったご家庭だけでなく、すべての動物とその家族の暮らしを見守る立場にあります。
通院のたびに交わされるちょっとした会話や、健康チェックのなかに、飼育環境の変化や飼い主の不安が隠れていることもあります。
そうした「気づき」にいち早く対応できるのは、日々接している動物病院ならではの強みです。
さらに、信頼される存在として、保護団体やボランティアとの橋渡しとなることもできます。
見守りの起点として、病院が地域の中で自然なハブとなることが理想ではないでしょうか
おわりに
譲渡時には万全だったはずのご家庭でも、時間の経過とともに支援が必要になることはあります。
だからこそ、譲渡を「ゴール」ではなく「スタート」と捉え、人と動物が安心して暮らし続けられるような仕組みを育てていくことが必要です。
見守るという姿勢は、保護譲渡に限らず、すべての動物家庭に向けたまなざしでもあります。
動物病院がその拠点となり、困ったときに相談できる存在として機能していけるよう、日々の関わりの中に優しさと備えを織り込んでほしいと願っています。